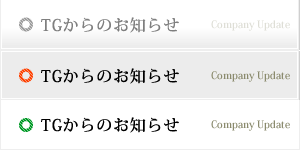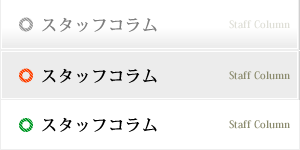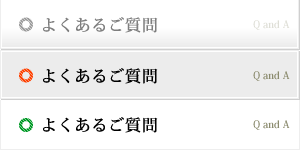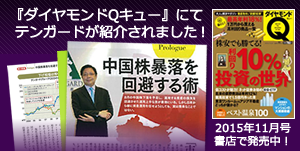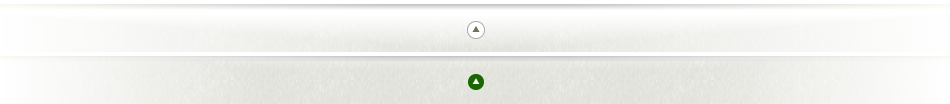米国企業の国有化で死のスパイラルに陥るか
- テンガードホールディングスリミテッド
スタッフコラム
米国企業の国有化で死のスパイラルに陥るか
[2025年9月2日]

かつて、米国が絶頂期にあった頃、政府は一貫して自由市場の旗を掲げ、独占に反対し、競争と民間の活力こそが国力の源泉であると信じて各分野の民営化を推進してきた。ところが最近、その風向きが変わりつつあるようだ。ワシントンからは、経営難に陥っている伝統的な米国企業の政府による株式取得の可能性が伝えられている。対象は鉄鋼や航空機メーカーのロッキード・マーティン(Lockheed Martin)から、さらにはインテル(Intel)のようなハイテク企業にまで及び、“国有化”への静かな歩みを思わせ、大きな議論を巻き起こしている。
この方向転換は、現実的な理由に基づいている。米政府がこれらの企業の株式取得を検討する背景には、主に戦略的な必要性と雇用の維持という二重のプレッシャーがある。まず、基幹産業が崩壊すれば国家の経済安全保障や技術的自立が脅かされるという懸念。そしてもうひとつは、資本注入によって雇用を守り、大規模な失業が社会不安を招くことを避けたいという思惑である。とりわけ、世界的なサプライチェーン再編や国際競争の激化という状況下で、政府は資本介入で安定を図ることをやむを得ない応急手段であると考えているようだ。
しかし、このアプローチは必ずしも賢明とは言えない。第一に、政府による投資は必然的に政治が企業経営に介入することを意味し、意思決定が市場原理から逸脱しやすくなる。政策目標や一時的な世論の迎合に至る可能性も高い。第二に、国有化はしばしば効率低下やイノベーション停滞を招く。政府の支援を受けた企業は生き残りをかけて戦うどころか、後ろ盾に甘んじて改革の意欲を失いかねない。さらに懸念されるのは、本来であれば淘汰されるべき企業を納税者の資金で延命させることによって、公共財の浪費にとどまらず、市場競争の歪みを生み、資源の流れを活力ある新興分野から阻害する可能性があることだ。
総じて見れば、米国がこれまでの民営化と競争促進の方向から転じて、政府資本による企業救済に乗り出すことは、一見して延命策に見えるかもしれないが、結果的には国家の衰退を加速させかねない。失敗した企業は国有化によって健全性が改善されるわけではなく、むしろ官僚主義が拡大し、制約が増し、柔軟性を失って、急速に変化する国際環境に対応できなくなる可能性がある。多くの国がこの道を歩んでおり、教訓を残してきたのは明らかだ。政府の役割は本来、最低限の規制を整えることであって、競技そのものに介入することではないはずだ。そうでなければ、短期的な救済策は長期的な衰退につながる可能性があるだろう。
- コラム
- お知らせ
- Q and A
証券取引委員 (SFC:Securities and Futures Commission) の Type 4, 9 のライセンスを取得しているファイナンシャルアドバイザーです。
香港強制性公積金計劃管理局 (MPFA: Mandatory Provident Fund Schemes Authority) の正規取扱代理店です。
香港保険業監管局 (IA: Insurance Authority) に正式登録されているライセンス保有代理店です。