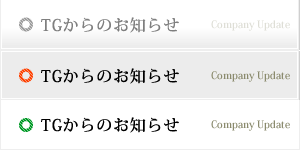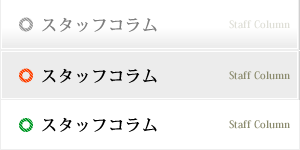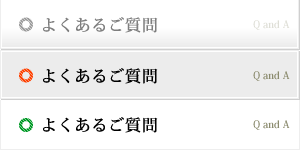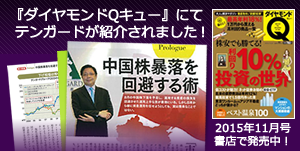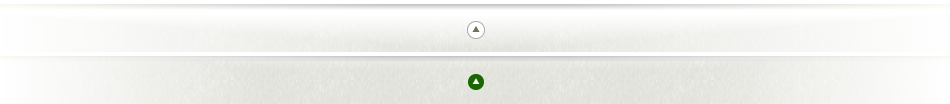日本株の上昇が必ずしも経済回復をもたらすとは限らない
- テンガードホールディングスリミテッド
スタッフコラム
日本株の上昇が必ずしも経済回復をもたらすとは限らない
[2025年11月6日]

現在の経済環境において、日本株市場が明確な上昇傾向を示しているものの、それが必ずしも経済全体の改善につながるとは限らない。以下に、注目すべきいくつかの主要な理由を挙げる。
日本経済は株式市場と連動していない
一般的には、株式市場の回復は経済回復の強力な指標と見なされるが、日本の場合、この見方は当てはまらない。日本の経済成長は依然として力強さに欠け、企業の設備投資や家計の消費支出も安定的な回復を見せていない。その結果、経済全体の活力不足が続いている。
長年の株価低迷で個人投資家の参加が減少
過去10年から20年にわたる株価低迷を経て、多くの日本人は株式投資に対して慎重な姿勢を取り、再び資金を投入することを避けている。そのため、一般市民の株式市場への参加率は著しく低下しており、今回の株価上昇によって恩恵を受けた人はごくわずかにとどまっている。結果として健全な経済循環が形成されず、経済全体の活力にもつながりにくい。
円安により「株による資産効果」に疑問
円安は一部の輸出企業にとっては追い風となっているが、実際には一般市民の実質購買力を弱め、消費支出の減少を引き起こす可能性がある。株価が上昇しているにもかかわらず、このいわゆる「資産効果」は国内経済の成長を十分に押し上げることができていない。結局のところ、外貨に換算すると資産価値は大きく目減りしており、消費や投資を刺激するのは容易なことではない。
少子化・高齢化が経済失速の主因であり、株高では解決できない
日本は深刻な人口問題に直面しており、少子化と高齢化により労働力供給が逼迫し、経済の勢いが急速に低下している。たとえ株式市場が上昇しても、この現象ではこうした深層的な構造的問題を効果的に解決することはできない。したがって、これが経済の長期的な回復を実質的に促進することを保証するものではない。
総じて、株式市場の力強い上昇は注目を集めているが、真の経済回復を実現するには、社会構造の抜本的な見直しや消費者信頼の再構築など、多方面での課題克服が必要である。このような状況下で、株価の動向だけに依存しても、経済全体の回復を効果的に促すことは難しいだろう。
- コラム
- お知らせ
- Q and A
証券取引委員 (SFC:Securities and Futures Commission) の Type 4, 9 のライセンスを取得しているファイナンシャルアドバイザーです。
香港強制性公積金計劃管理局 (MPFA: Mandatory Provident Fund Schemes Authority) の正規取扱代理店です。
香港保険業監管局 (IA: Insurance Authority) に正式登録されているライセンス保有代理店です。